
リードナーチャリングとは、自社で獲得した見込み顧客の購買意欲を引き上げるためのマーケティング活動のことです。
そのために、「メール送信」「セミナー/ウェビナー」「資料の提供」といった施策を行います。
シャノンのマーケティングチームでも、リードナーチャリング施策を継続してきました。そこで得られた成果の一例がこちらです。
「リードナーチャリングによって、ウェビナーの参加者を55%増やせる」
このとき行ったのは、メール施策です。具体的な方法は本文最後のパートでご紹介します。
今回は、「リードナーチャリングとは何か」「なぜ必要なのか」について基本からわかりやすく解説。
さらに、リードナーチャリング施策の種類と方法、実践のための5つのステップ、MAツールの活用方法、最後に成果があったリードナーチャリングの事例について紹介していきます。
▼これからリードナーチャリングへ挑戦するかたへ、まずは読むだけで全体の流れを整理していただける資料もご用意しております。

リードナーチャリングとは? メリットとデメリットは何か
リードナーチャリングとは何か、リードジェネレーションとの違いなど、基本的なことをまず確認します。
リードナーチャリングとはなにか
リードナーチャリング(Lead Nurturing)の「lead」は見込み顧客、「nurture」は、育成という意味なので、直訳すると「見込み顧客を育てること」となります。
見込み顧客に対して定期的にメールを送信したりセミナーやウェビナーを実施することで、自社製品やサービスへの理解を深めてもらい見込み顧客の購買意欲を高めることがリードナーチャリングの目的です。
BtoBマーケティングでは認知から購入までの期間が半年~1年程度とBtoCに比べ長い傾向にあり、この間に見込み顧客をフォローするリードナーチャリングの仕組みが重要になります。
シャノンでは、リードナーチャリングを「顧客の引き上げ」と表現しています。下の図の三角形はシャノンが提案しているフレームワークで、顧客の購買行動を「認知、興味、関心、比較・検討、商談」というフェーズで管理する「購買ピラミッド」といいます。リードナーチャリングはこのフェーズ管理の仕組みを利用することで円滑に進めることが可能になります。

リードナーチャリングでは、顧客の興味・関心を引き上げるために、さまざまな施策を実施します。
リードナーチャリングのメリットとデメリット
リードナーチャリングのメリットとデメリットを整理します。
《リードナーチャリングのメリット》
商談化率を上げ、CAC(顧客獲得単価)を抑えられる
最も大きなメリットは、獲得した見込み顧客のうち商談化まで進む割合を増やせることです。その結果、一顧客を獲得するために要するコストであるCACを抑えることができます。

顧客ロイヤリティを高める効果が期待ができる
見込み顧客に対して価値ある情報を届けるコミュニケーションを継続し顧客となった場合、すでに製品・サービスへの理解が深まっているため解約されにくくなる効果が期待ができます。
《リードナーチャリングのデメリット》
施策が多岐にわたり、リソースがかかる
リードナーチャリングの施策は多く、施策の実行だけでなく検証、改善などの作業も発生します。
特にリードナーチャリングをスタートさせるときは、コンテンツ作成に多くのリソースを必要とします。
リソース不足の対策として、MA(マーケティングオートメーション)の導入や外部パートナーの活用が有効です。
成果を上げるためには改善が必要
メルマガ配信、ウェビナー開催などで見込み客の引き上げを図っても思うように成果が上がらないこともあります。結果を検証して改善を重ねることで、次第に成果を上げられるようになりますが、それまでに一定の時間を要します。
リードナーチャリングとリードジェネレーションの違い・関係性
リードナーチャリングとリードジェネレーションとの違いを整理します。
リードジェネレーションとは、「見込み顧客の獲得」のことです。
リードジェネレーションの段階では、Web広告や自然検索から自社サイトへのアクセス、セミナー/ウェビナーへの参加、展示会での名刺交換などにより幅広くリードを獲得します。
ここまでが、リードジェネレーションです。
リードナーチャリングは、リードジェネレーションのあとに始まる「顧客の引き上げ」です。
リードの中には、すぐに購入を検討したいという「ホットリード」もいますが 、多くは「コールドリード」です。
Marketing Sherpaの調査 によると、獲得した顧客のうちすぐ購入にいたるのは1割程度であるのに対して、約7割の顧客は長期フォローが必要とされています。
長期フォローを必要とするのはどのような顧客でしょうか 。
具体的には、サービスや製品に興味があり問い合わせた人、購入前の情報収集のため資料をダウンロードしたウェビナーに参加した人などが当てはまります。そのなかに、「来期の予算で購入を検討したい」あるいは、「数社のツールをじっくり比較検討してから決めたい」といった「未来のホットリード」が存在します。
見込み顧客に対して長期で適切なフォローをすることにより、未来のホットリードを取りこぼさないようにするのが、リードナーチャリングです。
リードジェネレーション、リードナーチャリングのあとに、有望な顧客を絞り込むリードクオリフィケーションというステップもあります。3つの流れは以下の通りです。

リードジェネレーション、リードクオリフィケーションについては以下の記事を参照してください。
参考:
リードジェネレーションとは?MA(マーケティングオートメーション)で効果的に見込み顧客を獲得する手法と事例を紹介
リードクオリフィケーションとは?商談の成果を上げるための分析と4つのポイントをご紹介
リードナーチャリングの具体的な施策とMAツールの役割
リードナーチャリングの主な施策と、それらを効率よく実施するためのMAツールについて解説します。
リードナーチャリングの施策
リードナーチャリングの主な施策として、以下があります。
メール配信
取得したメールアドレスに対して定期的にメルマガを配信するだけでなく、リードの興味・関心に合わせて内容の違うメールを送信したり、特定のリードにセミナー/ウェビナーの案内をしたりといった「セグメントメール」の施策を行います。
MAツールを導入すれば、「シナリオ機能」により条件に応じたメール送信を自動化できます。また、リードがメールを開封、文中のURLをクリックなどのアクションをした履歴を蓄積して、次の施策に活かすことができます。
参考:メールマーケティングの種類や手法を解説。180%集客がアップした、メールマーケティングのコツもご紹介!
ウェビナー/セミナーの開催
ウェビナーやセミナーは、リードの興味・関心を一気に引き上げることができます。
告知にセグメントメールを活用してウェビナーの集客がアップした事例については後述します。
参考:ウェビナーで集客する8つの方法とは?集客で失敗しないための6つのポイントも解説
ホワイトペーパー
リードにとって有用な情報をWebからダウンロードできる「ホワイトペーパー」は、企業がメールアドレスを取得するためのリードジェネレーションの施策として活用されますが、リードナーチャリングの施策としても有効です。
興味・関心がある見込み顧客向けのホワイトペーパーとしては、ターゲットの課題を解決できるようなお役立ち資料が適しています。
参考:ホワイトペーパーとは?BtoBマーケティングでの活用方法・効果を上げるための5つのアイデアを紹介
Webサイト閲覧履歴の収集
MAツールにより、リードが自社のWebサイトのどのページを訪れたかの履歴を記録できます。
オウンドメディアを訪問しているリードは認知レベル、活用事例のページを見たリードは興味・関心レベル、商材の価格ページを見たリードは比較・検討レベルと判定できます。
履歴をもとに、有効な次へのアプローチを行います。
Web広告
以前自社のWebサイトなどを訪れたことがあるが、その後しばらくの間訪問がないリードに対しては、Web広告が有効です。SNS広告やディスプレイ広告のリターゲティング広告が適しています。
参考:Web広告の種類と役割、効果的な運用方法を紹介!
インサイドセールス
インサイドセールスは、直接顧客と会う営業部門と異なり、電話やオンライン等の手段で見込み顧客にアプローチする営業職です。
インサイドセールスの役割は企業によって違いますが、リードナーチャリングの最終段階において、興味・関心度が高まっているリードをさらに商談可能な状態まで引き上げる、重要な役割を担当することが一般的です。
参考:インサイドセールスの役割とは?導入のメリットと手順、応答率を上げるコツも紹介!
DM
しばらくアクセスがないリードに対しては、直接手元に届くDMが有効な場合もあります。展示会やウェビナーの案内、サービス導入事例などを送付することが多いです。
参考:ダイレクトメール(DM)の取り組み方や効果を高める方法は?成功事例も紹介
リードナーチャリングではこれらの施策を組み合わせ、それぞれの顧客の興味・関心度に合わせた引き上げ施策を行っていきます。
MAツールとは?なぜ、BtoBのリードナーチャリングに有効なのか
MA(マーケティングオートメーション)は、リードナーチャリングの各種の施策を自動化・効率化できるシステムツールです。
リードナーチャリングにMAツールが有効な理由として、以下が挙げられます。
業務効率化ができる
リードをきめ細かくセグメント分けして長期的にフォローする作業には手間がかかりますが、MAツールによりその大部分を自動化できます。
見込み客のホームページへのアクセス、メールの開封、展示会来訪などの行動履歴を一元管理。何らかのアクションがあったリードにメールを送信する施策をシナリオ機能で設定することもできます。
業務効率化により、マーケティング担当者はより高度なマーケティング戦略に取り組む時間を増やせます。
参考:MAのシナリオ機能とは?シナリオを作成するメリット、手順、シャノンが実践しているシナリオ事例も多数紹介!
過不足のない、顧客目線のアプローチができる
見込み顧客にとって興味のない内容のメールマガジンが頻繁に送信されると、送信元企業に対してマイナスの印象を持ってしまう可能性があります。
MAツールにより、見込み客それぞれの興味・関心の段階に合わせて異なるメールを適切なタイミングで送る仕組みを自動化できるので、「メールが多すぎる」という印象を与えにくく、有効な情報を見てもらえる可能性は高くなります。
タイミングを逃さずホットリードをフォローできる
有望な見込み顧客は競合会社の商材も同時に比較検討していることが多いので、具体的な検討段階に入ったリードに対しては他社に先駆けてアプローチすることが重要です。
たとえば、商材の資料請求や料金表の閲覧などのアクションはホットリードのサインといえます。MAツールはこうしたアクションがあったときに担当者に通知を送る設定ができるので、タイミングを逃さずにセールス部門に情報を渡すことができます。
参考:ホットリードを商談につなげる!ナーチャリングを最適化するスコアリング方法のコツと注意点を解説
長期にわたり安定的・継続的なフォローができる
BtoBのリードが実際の顧客となるまでには半年~1年程度、商品やサービスによってはそれ以上の期間を要します。また、一度ウェブサイトを訪れただけのコールドリードが1年以上を経た後に復活し、ホットリードとなることもあります。リードナーチャリングが長期にわたるケースでもMAのシナリオ設定により、着実にフォローできます。
ノウハウの属人化を防げる
見込み客を長期にわたってフォローするリードナーチャリングでは、担当者が途中で交替することもあります。MAを導入していれば、そんなときもノウハウが属人化することなく、業務のデータをスムーズに引き継ぐことができます 。
多様なワークスタイルに対応でき、将来のDXにもつながる
コロナ禍以降、自社担当者・顧客どちらもリモートワークということが珍しくない状況が、企業のDX(デジタルトランスフォーメーション)を促進しています。将来のDXに備えるためにも、MAツールが有効です。また、リモートやサテライトオフィスなどワークスタイルが変化しても、MAツールがあればスムーズに仕事を継続できます。
※参考:
DX とは何かをわかりやすく解説!今、企業はDXをどう進めている?
マーケティングDXとは?【前編】定義やメリット、進め方、企業事例を紹介

リードナーチャリングの手順5ステップ
リードナーチャリングの具体的な5つのステップを順にご紹介します。
【STEP1】 リードナーチャリングの第一歩は、「名寄せ」によるリードの集約
リードナーチャリングでまず必要なのは「リードの集約と管理」です。
リードジェネレーションで獲得したリードは、様々なチャネルから集められています。たとえば、自社ホームページからの資料ダウンロード、展示会で交換した名刺、ウェビナーの参加者などです。
ある企業の担当者が資料ダウンロードをしてかつ、展示会にも参加していたとしたら、かなりのホットリードといえます。
しかし、会社名が「株式会社××」と「××」のように異なるために別々のリードとして管理されていたとしたら、このホットリードを見つけることができません。BtoBでは会社名、役職名、住所など基本データ項目が多いので、適切に「名寄せ」する作業が重要です。

シャノンのMAツールでは、たとえば以下のようなデータ表記の違いを整理するルールを自動化することができます。
・半角と全角を統一
・大文字と小文字を統一
・法人格と会社名を分割
・法人格の略称を統一
また、「人」と「企業(会社名)」を紐づけて管理するルールを設定することもできます。
このようにして、精度の高いリードデータを得ることを、データクレンジングといいます。
参考:データクレンジングとは?マーケティング施策成功のために欠かせないデータクレンジングの手順
【STEP2】 企業や商材に合わせた「購買ピラミッド」を設計する
リードナーチャリングでは、自社の商材のことを最初に認知したリードが、その後どのような過程を経て商談までいたるかというシナリオを用意します。
前述した「購買ピラミッド」のなかにリードを落とし込み、「認知」「興味・関心」「比較・検討」「商談」といったリードのフェーズごとに適したマーケティング施策を行います。

リードの多くは当初、購買意欲が低い「認知」レベルに該当します。しかしリードナーチャリングにより、何割かは興味と関心を深め、やがて比較・検討の段階を経て商談へと進んでいきます。
購買ピラミッドのフェーズ分けは、企業の業種や売ろうとしている商材によって異なるので、今までの顧客実績をもとに、自社に合った形で設計する必要があります。
たとえば、
「ウェビナーに参加した後に具体的な検討に入るリードが多い」
「最初に商品のことを知ってから、約半年後に商談を開始し購入に至るリードが多い」
「資料をダウンロードしても、その後半年以内に再度のアクセスがないリードは見込みが薄い」
など、自社の顧客に共通するいくつかの行動パターンをピックアップして、購買ピラミッドのシナリオに落とし込みます。
この設計図に基づき、各リードがどのフェーズにあるかを明確にして、施策として「いつ、何をするか」が決まります。
参考:MAのはじめかた、肝になるのは購買ピラミッドの全体管理
【STEP3】 マーケターが最も悩む「スコアリング」はシンプルに設定する
リードナーチャリングでは見込み客のフェーズを客観的に評価するために、顧客行動を数値化する「スコアリング」を実施します。
以下はスコア設定の具体例です。
・自社に対する認知の程度によって5点または10点
・1か月以内にWebにアクセスがあれば引き続き興味を持っているということで10点
・リードがマーケティング部門に所属していれば10点

スコアリングでは各項目に何点をつけるのかが悩む所です。
スコアリングについては、リードナーチャリングの開始時点では明確な基準は存在しません。どんな要素がホットリードの決め手となるかは、個々の企業・商材によって異なるからです。
初期段階においては、スコアは「1アクションにつき各10点」のように、シンプルに設定することがおすすめです。理由はどの項目が有効か分析しやすく、後から設定を見直しやすいからです。
スコアリングで高得点となったリードは「商談可能」なホットリードと判定して、営業部門に引き渡すことになります。引き渡し後にホットリードのなかでも成約、保留、失注と結果が分かれてくるでしょう。そうした結果をフィードバックして、スコアリングを修正することで精度を上げていきます。
参考:MAで必須の「スコアリング」はかなり難しい。BtoBマーケティングを成功に導くスコアリングのポイントは?
【STEP4】 顧客ごとに異なるOne to Oneマーケティングの実践
One to Oneとは、各リードが自社商材に対してどの程度に関心を持っているかを明らかにして、各リードの現在の関心の程度に合わせた情報を届けることです。
たとえば、購買意欲が高いホットリードには「同業種の導入事例」「オンラインデモの案内」のような、次のフェーズへと進めるためのメールを配信します。
一方、配信済メールの開封がなかったコールドリードに対しては、別の商材を案内するメールを送信したり、定期的なメールマガジンの配信をしたりしながら、長期でフォローを続けます。
One to Oneマーケティングにより、各リードに対して最も必要としている情報をタイミングよく届け、かつ、不要な情報が届くことによってもたらされるマイナスの効果を減らすことができます。
では、各フェーズでどんなアプローチするためにはどんなコンテンツが必要なのでしょうか?それぞれのコンテンツに必要な要素ならびに適したチャネルはぜひ以下の画像をご参考ください。

参考:One to Oneマーケティングとは? MAで効率化できるその具体的手法を解説
【STEP5】 STEP1~4を実践し、PDCAを回す
リードナーチャリングの精度を高め、成果を上げていくためには、運用しながら定期的に効果測定をすることが大切です。PDCAを回し、当初のシナリオ通りに成果が出ていない「スコア」や「シナリオ」を修正し、修正した設計から結果を得たら前回との比較でさらに検証を重ねます。
こうした過程を経て、自社に適したリードナーチャリングの制度設計ができあがっていきます。BtoBでは購入までの検討期間が長いので、こうした作業にもかなり時間がかかりますが、じっくり取り組む姿勢が必要です。
リードナーチャリングの施策には今回具体例を挙げなかったものも多数あります。ウェビナーなどのイベント、広告への反応など、多くの施策に対するリードのリアクションを統合管理することを「キャンペーンマネジメント」といいます。
参考:キャンペーンマネジメントとは?MAツールで効果的な1to1マーケティングを実現
リードナーチャリングで成果を上げるポイント
リードナーチャリングの施策の種類は多岐にわたり、それらを着実に進めていくことは簡単ではありません。成果を上げるポイントとして、以下が挙げられます。
施策ごとにKPIを設定して、効果測定と改善をする
KPIとは、「Key Performance Indicator」の略で、日本語では「重要業績評価指標」などと訳されます。KPIは、業務の成果を定量的に測定するための重要な指標で、中長期的な時間軸で達成度を測ります。
リードナーチャリングでは、例えば以下のようなKPIを設定します。
・半年以内に「興味・関心」から、「比較・検討」フェーズへと進むリードが15%
・ウェビナーの案内メール/ウェビナー開催レポートのURLをクリックするリードが10%
・メールマガジンの開封率が15%
・半年以内にホットリード(50点以上のスコア)となるリードが5%
リードナーチャリングの担当者は、KPIを設定し、それを達成するためにどうするかという観点から、シナリオや施策を構築していきます。
もうひとつ、目標設定で重要なことは、他部門との連携です。
リードナーチャリングにおけるKPIは、設定するのはマーケティング部門だったとしても、営業部門や上長など関連するすべての部門やメンバーに共有されることが重要です。
BtoBのリードナーチャリングは成果が出るまでに時間がかかるということにも、具体的な数値を示しながら理解を得ておく必要があるでしょう。
参考資料:マーケティングオートメーション時代に必要な15のKPI
施策のターゲットを明確にする
リードナーチャリングの各施策は、ターゲットを明確にすることで結果が出やすくなります。
購買ピラミッドの「興味・関心層」と、「比較・検討層」に対しては施策を分けることがおすすめです。
たとえばウェビナーの場合、購買意欲が高い比較検討層向けには具体的な導入検討に役立つ製品ウェビナー、購買意欲は低いが興味のある興味関心層向けには業務の課題解決に役立つ関心ウェビナーを用意します。

シャノンでは「製品ウェビナー」と「関心ウェビナー」を分けてを実施した結果、製品ウェビナーは集客が少ないがアポイント率は高く、関心ウェビナーはアポイント率が製品ウェビナーに劣るものの多くの集客が可能である、ということがわかりました。
そして、関心ウェビナーに参加した人の一定割合を引き上げて製品ウェビナーへ誘導する流れをつくることができました。
同じように、メールやホワイトペーパーの施策でも、見込み客のフェーズに合わせたコンテンツを提供していくことが有効です。
ABテストで施策を実行しながらブラッシュアップしていく
集客力のあるコンテンツはどんなものかは、実際に施策を進めていくなかで少しずつわかってきます。
たとえば毎週送付するメールマガジンなら、開封率が高いメールのタイトルやコンテンツというのが見えてきます。
そこからさらに進んで、効果があるコンテンツを明確に判定するのが「ABテスト」です。
ABテストとは、A案とB案のどちらの方が効果があるかテストすることで、たとえば以下のような施策で活用されています。
・キービジュアル、レイアウト、キャッチコピー、動画の有無など、Webページのコンテンツ
・メルマガのタイトル、メルマガのレイアウト
・メルマガを送信する曜日、時間帯
・ウェビナーのタイトル
ABテストを重ねることにより、各施策でより高い効果を上げていくことができます。
参考:ABテストとは?メリット・デメリットや具体的な進め方を解説。ツールや事例も一挙紹介!
各フェーズに対応できる施策をモレがないように整える
前述のとおり見込み顧客の購買意欲の程度はさまざまで、それぞれに対して有効な施策が必要です。
リードナーチャリング施策が自社の見込み客を確実にフォローできているか?をチェックすることで、施策の不足を発見できることがあります。
以下は、施策を整理するためのチェックシート例です。
「フェーズの整理」では、購買ピラミッドのひとつ下からリードがどのくらいの割合で引きあがったかが見え、「ナーチャリング施策」では施策が足りていないフェーズが分かるようになります。

上記の図では、見込み顧客の「関心層」への引き上げが他のフェーズと比較し少なく、施策を見ると「関心層」向けのホワイトペーパー、関心ウェビナーの施策が実施されていないことがわかります。
この場合、その上の「比較・検討層」まで見込み客が引き上げられる機会がない、ということになってしまいます。
リードナーチャリングで成果を上げたシャノンの事例
最後に、リードナーチャリング施策の成功事例をいくつかご紹介します。
ウェビナーの集客を55%増やしたセグメントメール
冒頭で紹介した「ウェビナーの集客」を55%高めることができたメール施策について解説します。
以下のように、一般のメルマガに加えて「セグメントメール」を2回送信しています。

セグメントメールとは対象を絞り込んで送信するメールです。このときは、
・「1年以内にウェブアクセス履歴あり」の対象者へ向けてウェビナー案内の単独メールを送信
・「LP着地履歴あり」の対象者へ直前に再案内のメールを送信
という施策を実施しました。
メルマガ経由で参加した人とセグメントメール経由で参加した人の比率を集計したところ、セグメントメールにより55%集客数を上積みできました。
フォーム落ちの顧客を自動メールで呼び戻す
ホワイトペーパーのダウンロードフォームまで閲覧したが、登録とダウンロードをしないままになってしまう「フォーム落ち」のリードに対しての施策です。

フォーム落ちのリードに対して翌日自動でメールを送信するよう、MAのシナリオを設定します。
メールにはダウンロードするメリットを端的に伝えるメッセージとURLを掲載。
資料に対する興味が失われないよう、翌日スピーディーにフォローすることがポイントです。
電話フォローで商談化件数を増やす
シャノンでは購買ピラミッドの上位に位置する「比較・検討層」のリードに対して、具体的に購買を促すための「製品ウェビナー」を行い、実施後に「参加者に電話をしてリードを商談化まで引き上げる」という施策を行ってきました。
しかし、「電話応答率が低い」という課題がありました。
そこで、ウェビナー講師とフォロー担当者を分けていた運用を改めました。「ウェビナー終了時に、講師から電話があることを伝え、ウェビナー講師が電話フォローまで行う」という方法に変更したところ、以下のように応答率が約20%から60%前後まで向上しました。

このように、リードナーチャリングはMAで行うデジタルな施策のみというわけではなく、電話フォローのようなアナログ施策も実施しながら改善を続けています。
まとめ
本稿のポイントは以下の4点です。
1. リードナーチャリングとは、リードジェネレーションで獲得した見込み客を顧客へと引き上げることです。特にBtoBマーケティングでは、購入までの期間が1年程度と長くかかる傾向にあるので、この間に適切な情報を届けるリードナーチャリングが有効です。
2. リードナーチャリングの施策として以下があります。これらを効率よく確実に実施するためにMAツールが有効です。
・メール配信
・ウェビナー/セミナーの開催
・ホワイトペーパー
・Webサイト閲覧履歴の収集
・Web広告
・インサイドセールス
・DM
3. リードナーチャリングの5ステップは以下の通りです。
【STEP1】 リードナーチャリングの第一歩は、「名寄せ」によるリードの集約
【STEP2】 企業や商材に合わせた「購買ピラミッド」を設計する
【STEP3】 マーケターが最も悩む「スコアリング」はシンプルに設定する
【STEP4】 顧客ごとに異なるOne to Oneマーケティングの実践
【STEP5】 STEP1~4を実践し、PDCAを回す
4. リードナーチャリングで成果を上げるポイントとして、以下があります。
・施策ごとにKPIを設定して、効果測定と改善をする
・施策のターゲットを明確にする
・ABテストで施策を実行しながらブラッシュアップしていく
最後に、シャノンのマーケティングオートメーションでは、データの一元管理による効率的なリード獲得とナーチャリングが可能です。
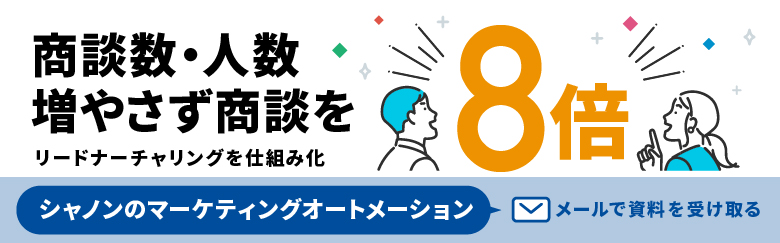
また、シャノンコンテンツアシスタントでは、主にセミナー集客メールのタイトルと内容、記事集客メールのタイトルと内容、記事本文の生成が可能です。
⇒マーケティング専用 生成AIクラウドのサービスサイトはこちら













