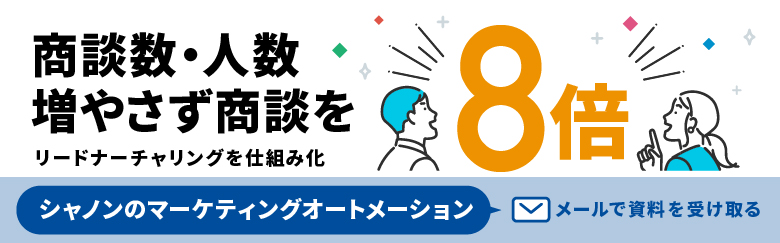みなさま、こんにちは。シャノンの中村です。
「展示会は毎回胃が痛い」「費用対効果が見えにくい」 BtoB企業のマーケティング担当者なら、誰もが一度は感じたことのある悩みではないでしょうか。
多額の費用と労力を費やす展示会ですが、その成果を最大限に引き出すためのオペレーションは、意外と見過ごされがちです。
この記事では、年間で大小あわせて20回以上の展示会出展経験を持つシャノンが実践する、展示会オペレーション改善のノウハウをご紹介します。
会期前の準備でリード獲得を加速させる
ウェブサイトへの出展情報掲載だけではなく、さらに一歩踏み込んだ施策で来場意欲を高め、質の高いリード獲得を目指しましょう。
訪問確度の高い見込み客を炙り出す「事前架電」
ウェブサイトに展示会出展情報を掲載したら、必ずハウスリストへのメール配信を行いましょう。
マーケティングオートメーションツールを活用すると、誰がその出展情報ページをクリックし、閲覧したかを把握できます。
次に重要なのが、この閲覧者への「架電」です。
「え、電話なんてするの?」と思われるかもしれませんが、ご安心ください。
目的はあくまで来場を促すことであり、無理な売り込みは一切不要です。

架電内容の例: 「来週開催される〇〇EXPOに出展しますので、ぜひご来場いただきたくお電話いたしました。」
この一言で、見込み客の反応は大きく4つに分かれます。
- 「行けない」:今回は参加できない。
- 「興味はあるが未定」:スケジュール次第で行きたい。
- 「行く予定だが日程未定」:〇月〇日のどこかで行くつもり。
- 「行く予定(日程確定)」:〇月〇日に行く予定。
この情報を当日接客するメンバーと共有することが非常に重要です。
特に「興味はあるが未定」「行く予定」の顧客には、来場する可能性があることを伝えることで、営業担当者の心構えができます。
追いかけている顧客が来場予定と分かれば、営業は準備を整え、万全の体制で対応できます。
こちらの施策は、小規模ブースこそ効果的です。
大規模ブースでは、電話担当者と接客担当者が異なるケースも多いですが、小規模ブースであれば、電話をした担当者がそのまま接客できる可能性が高まります。
「来てくださったんですね、ありがとうございます!」という言葉からはじまる接客は、顧客に好印象を与え、翌週のフォローもしやすくなります。

電話でのアプローチが難しい場合は、閲覧者に対して再度来場を促すメールを配信するだけでも、来場意欲を高める効果が期待できます。
来場者以外も「見込み客」としてフォロー
展示会後のフォローを来場者だけに行っていませんか?
実は、出展情報ページを閲覧したものの来場しなかった顧客こそ、大きな見込み客となる可能性があります。
来場しなかった顧客にもフォローをおすすめする理由は、以下2つです。
- 出展情報ページをわざわざ見に来たということは、自社への何らかの関心がある
- 遠方で参加できない、当日都合が悪くなったなど、来場できないだけでニーズが全くないわけではない
来場者へのお礼メールと同様に、開催レポートやダウンロード資料を案内するメールを送付し、その反応があった顧客は優先的にフォローしましょう。

会期中の「オペレーション」を見直して取りこぼしを防ぐ
会期中のオペレーションは、限られた時間で最大限の成果を出すために非常に重要です。
特に見直すべきは「リードの評価基準」と「情報入力フロー」です。
「ホット・ウォーム・コールド」の定義を再構築する
多くの企業で導入されているリード評価基準(ホット・ウォーム・コールドやABC判定など)ですが、その定義が曖昧だったり、担当者間で認識がずれていたりするケースがあります。

みなさまの会社でこのような問題は起きていませんか?
- 部署によってホットの定義が異なる。
- 目標数にあわせて、無理やりホットに分類してしまう。
これらの問題は、明確な定義ができていないことに起因します。
以下の基準を参考に、判断軸を定義してみてください。
- 「具体的な検討段階か」「予算化しているか」など、商談につながる可能性を基準にする。
- 「課題が明確か」「漠然とした課題感か」など、顧客の状況を基準にする。
- 「アポイントOKならホット」「資料請求OKならウォーム」など、次のアクションにつながる基準にする。
これらの軸は、説明員のスキルセット(ベテランが多いのか、新卒が多いのか)によっても調整が必要です。
「コールドは全然追えない…」という悩みを抱えている企業は、コールドの定義を見直しましょう。
コールドの中には「不明(ヒアリング不足)」「ニーズなし」「競合・除外」などが混在しているケースが多くあります。
特に「不明」のコールドリードは、今後商談につながる可能性を秘めています。
これを明確に分けることで、少なくとも確認の連絡を入れられるようになり、機会損失を防ぐことができます。
名刺とアンケートの入力オペレーションを最適化する
「接客に追われて入力がスムーズに進まない」「会期後のフォローをスムーズにしたい」といった声も多く聞かれます。
最近はスマホでの名刺スキャンやアンケート入力ツールが増えていますが、以下2つのポイントをもとに自社の環境に本当に合っているか見直す必要があります。
- 入力方法の慣れ: 若手スタッフはスマホ入力に慣れていても、ベテランスタッフは紙の方がスムーズな場合があります。
- 入力項目と分量: 入力項目が多すぎたり、自由に記述できる項目が多すぎると、入力に時間がかかりすぎ、次の来場者への対応が遅れる原因になります。
シャノンの場合は、「名刺はデジタル、アンケートは紙」というハイブリッド方式を採用しています。
それぞれの違いをご紹介します。
- 名刺: すぐにデジタル化し、お礼メールを迅速に送付するため。
- アンケート(ヒアリングシート): 紙で運用。物理的に書ける分量を制限し、簡潔に入力できるように工夫

アンケート情報を電話をかけるかどうかの判断や、商談前の簡単な確認程度でしか使っていないのであれば、過度な情報入力は非効率です。
展示会場での入力はあくまで参考情報と捉え、初回面談で改めてヒアリングを行うという割り切りも必要かもしれません。
重要なのは「回転率」 です。
オペレーションが複雑になればなるほど、接客の回転率が悪くなり、結果として名刺獲得枚数が減ってしまいます。
自社の接客員に合わせて、最適なオペレーションを構築しましょう。
会期中の「声がけ」と「ブース演出」で集客力を高める
「ブースに人が来ない」という悩みは、特に小規模ブースで顕著です。
予算が限られている中で、どうすれば集客力を高められるのでしょうか。
まずは「声がけ」を徹底する
意外とできていないのが「声がけ」です。
多くのスタッフが「何を話せばいいか分からない」「反応がないと心が折れる」といった理由で躊躇してしまいます。
声がけを強化するために実践できるノウハウをご紹介します。
- 複数人体制で恥ずかしさを払拭: 一人ではなく、二人以上で声がけを行うことで、お互いに刺激し合い、行動しやすくなります。
- 「声がけマニュアル」を作成: 「マーケティングオートメーションのシャノンです!」のように、決まった定型文を用意することで、何を話せばいいか迷わずに対応できます。これにより、反応がなくても個人的に落ち込むことを防げます。
- ノベルティとセットで声がけ: 「無料資料を配布しています」など、ノベルティとセットで声がけを行うことで、足を止めてもらいやすくなります。
小規模ブースこそ「プロ」の活用を検討する
予算の関係でブースプレゼンやコンパニオンの導入を諦めていませんか?
実は、小規模ブースこそ、プロの力を借りるメリットがあります。
- コンパニオン: 一定のテンションをキープし、効率的に声がけを行うプロです。少人数でも導入することで、ブースの雰囲気を明るく保ち、来場者の足を止めやすくします。
- ブースプレゼン: 大手企業のブースプレゼンが盛り上がるのは、「事前の知名度」と「プロの話術」があるからです。
- 知名度がない場合: 来場者が足を止めるための「初動の仕込み(サクラなど)」も検討が必要です。
- 話のプロ: セミナーでの登壇経験がある方もいますが、展示会のブースプレゼンは、より短時間で引きつける話術が求められます。実演販売士のようなプロに依頼することで、来場者の関心を惹きつけ、滞在時間を延ばすことができます。
短時間集中型のコンテンツ ブースプレゼンは、30分といった長尺ではなく、5〜10分程度に凝縮し、短時間でインパクトを与える内容にすることが重要です。
会期後のフォローは「MAツール」で効率化!
展示会終了後、営業がフォローをかけるのは翌月いっぱい、という企業が多いのではないでしょうか。
しかし、実はその2ヶ月後、3ヶ月後にこそ、大きな商談のチャンスが潜んでいます。
営業テンションが落ち着いた頃が狙い目
展示会直後は、多くの企業から電話がかかってきて、来場者側も対応に追われ忙しいものです。
しかし、会期から1〜2ヶ月後には来場者側も手が空き、落ち着いて情報収集できるタイミングが訪れます。

ぜひこのタイミングで効果的にアプローチしてみてください。
MA(マーケティングオートメーション)ツールのトラッキング機能があれば、会期から時間が経ってから自社のウェブサイトを再訪した顧客を把握できます。
営業が「今更電話しても…」と躊躇するタイミングで、顧客が自発的に情報収集をしているというサインを捉え、効率的にアプローチすることが可能になります。
営業がゼロから電話をかけるよりも、顧客の自発的な行動を捉えてアプローチする方が、商談化の確率は格段に上がります。
まとめ
展示会は、多大なリソースを投入する重要なマーケティング活動です。
その費用対効果を最大化するためには、ブースの規模や出展回数に関わらず、会期前から会期後までの一貫したオペレーション改善が不可欠です。
特に、中小規模の企業や、展示会運営に慣れていない企業様も、今回の内容を参考に、自社の状況に合わせた改善策をぜひ実践してみてください。